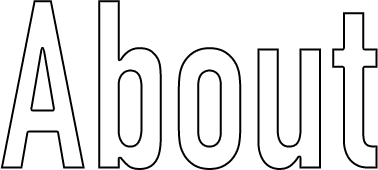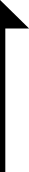日本の調味料について
平安時代に中国から伝えられた禅宗の影響を受け、菜食中心に歩みはじめた日本料理。その当時、淡白な大豆や野菜をおいしく食べるために花開いたのが現在に伝わるだしの文化でした。以降、日本の調味料は数世紀にわたる料理の発達とともに進化。砂糖、塩、酢、醤油、味噌、酒、みりんの7つを中心とした、さまざまな調味料が日本の味を演出しています。

醤油
大豆などの穀物から作られる日本を代表する調味料。起源は古く、すでに8世紀には祖先である「醤(ひしお)」が作られていたという記録が残されているほど。
その後、数世紀をかけて進化を繰り返し、江戸時代(17~19世紀)には現在とほぼ変わらない味と見た目の「しょうゆ」が庶民の間にも定着。まろやかな塩味と芳醇な香りが特徴のしょうゆは、日本料理になくてはならない存在となっています。


-
概要・歴史
大豆などの穀物から作られる日本を代表する調味料。起源は古く、すでに8世紀には祖先である「醤(ひしお)」が作られていたという記録が残されているほど。
その後、数世紀をかけて進化を繰り返し、江戸時代(17~19世紀)には現在とほぼ変わらない味と見た目の「しょうゆ」が庶民の間にも定着。まろやかな塩味と芳醇な香りが特徴のしょうゆは、日本料理になくてはならない存在となっています。使い方煮物や吸い物をはじめとする料理の調理段階における味付けに用いられるほか、食卓では焼き魚や刺身、寿司など完成した料理につける・かける「たれ」として、日本人なら口にしない日はないほどポピュラーなしょうゆ。
料理に深みのあるしょっぱさを添えてくれるだけでなく、肉や魚の生臭さを消す消臭効果や、素材の甘みを引き立てる効果、加熱することで食欲をそそる色や香りを生み出す効果など、さまざまな働きがあります。バリエーション-

濃口しょうゆ
-

淡口しょうゆ
-

溜しょうゆ
-

白しょうゆ
-

再仕込しょうゆ
出典:イチビキ公式ウェブサイト
-

めんつゆ
昆布や削り節などから取った出汁に、醤油や酒・みりん、砂糖などを加えて作る麺つゆは、日本の麺文化の発展とともに進化してきた調味料。今やそばやうどん、天ぷらのつゆとしてだけでなく、煮物や丼ものの味付けに使われるなどさまざまな和食になくてはならない存在になっています。市販の麺つゆにはそのまま使うストレートタイプのほかに水で割って使う希釈タイプもあります。


-
概要・歴史
昆布や削り節などから取った出汁に、醤油や酒・みりん、砂糖などを加えて作る麺つゆは、日本の麺文化の発展とともに進化してきた調味料。今やそばやうどん、天ぷらのつゆとしてだけでなく、煮物や丼ものの味付けに使われるなどさまざまな和食になくてはならない存在になっています。市販の麺つゆにはそのまま使うストレートタイプのほかに水で割って使う希釈タイプもあります。
使い方そば、うどん、そうめんをはじめとする麺類や、天ぷらなどのつけゆつ・かけつゆとして用いられるのが一般的。
また、つゆには、しょうゆ、砂糖、みりん、出汁などが含まれていることから、きんぴらごぼうや肉じゃがをはじめとする煮物や、親子丼、かつ丼などの丼物を中心に、幅広い料理の味を手早く決める万能調味料としても重宝されています。バリエーション-

そばつゆ
-

そうめんつゆ
-

うどんつゆ
-

天つゆ
-

ソース
文明開化とともに英国からもたらされ た「ウスターソース」を日本人好みにアレンジすることで 生まれたソースは、複数の野菜やくだもの、スパイス、酢 などが原材料。主に揚げ物などにつける「たれ」としての中濃ソース、とんかつソースをはじめ、焼そばソース、お好み焼きソース、たこ焼ソースなど、使う料理に特化したタイプも多数あります。


-
概要・歴史
19世紀の文明開化にともない英国からもたらされた「ウスターソース」を日本人好みにアレンジすることで生まれたソースは、複数の野菜やくだもの、スパイス、酢などが原材料。主に揚げ物などにつける「たれ」として用いられる中濃ソースをはじめ、とんかつ専用のとんかつソース、焼きそば専用の焼きそばソース、お好み焼き専用のお好み焼きソースなど、料理に特化したタイプも多数あります。
使い方あくまで“料理の風味付け”として数滴たらすだけの英国のウスターソースを、日本古来のしょうゆのように「つける・かける」調味料へとアレンジして生まれたソースだけに、完成した料理にかけるのが一般的です。
一方、カレーライスやハンバーグ、パスタソースなど調理段階に使う“隠し味”としても広く用いられます。バリエーション-

中濃ソース
-

ウスターソース
-

とんかつソース
-

焼きそばソース
-

お好み焼きソース
-

たこ焼きソース
出典:ブルドックソース(株)
-

出汁
昆布やかつお節、煮干しなどを、火にかけた水に入れて煮だしたスープのこと。その歴史は古くはるか奈良時代(8世紀)の文献にも「かつお節(と思われる食材)を朝廷へ献上した…」という記録が残されています。アミノ酸の一種であるグルタミン酸やイノシン酸、グアニル酸の働きによって、さまざまな料理に旨味を与えてくれるだしは、日本料理を支える屋台骨といえるでしょう。


-
概要・歴史
昆布やかつお節、煮干しなどを、火にかけた水に入れて煮だしたスープのこと。その歴史は古くはるか奈良時代(8世紀)の文献にも「かつお節(と思われる食材)を朝廷へ献上した…」という記録が残されています。アミノ酸の一種であるグルタミン酸やイノシン酸、グアニル酸の働きによって、さまざまな料理に旨味を与えてくれるだしは、日本料理を支える屋台骨といえるでしょう。
使い方そのまま味噌汁や吸い物、煮物、炊き込みご飯、だし巻き卵などさまざまな料理に用いられる出汁ですが、しょうゆや砂糖、みりんと合わせることで、そばやうどん、そうめんの「つゆ」のベースとしても欠かせない存在です。
一方、出汁の旨味で料理の塩分を補えられるというメリットを生かして、近年は健康増進に役立つ調味料としても注目を集めています。バリエーション- 昆布だし
- かつおだし
- いりこだし
- あごだし
- 白だし

味噌
大豆を蒸した(または煮た)ものに、麹と食塩を加えて、発酵・熟成させた半固体状の調味料。起源は諸説ありますが、古代中国の調味料「醤(ひしお)」などをもとに日本独自に発展した説が有力とされています。
味噌には、原料の違いによって「米味噌」「⻨味噌」「豆味噌」などがあります。味によって「甘味噌」「甘口味噌」「辛口味噌」、色によって「赤味噌」「淡色味噌」「白味噌」などに分類することもできます。


-
概要・歴史
大豆を蒸した(または煮た)ものに、麹と食塩を加えて、発酵・熟成させた半固体状の調味料。起源は諸説ありますが、古代中国の調味料「醤(ひしお)」などをもとに日本独自に発展した説が有力とされています。
使う麹菌によって「米味噌」「麦味噌」「豆味噌」などがある味噌は、さらに味によって「甘味噌」「甘口」「辛口」、色によって「赤味噌」「淡色味噌」「白味噌」などに分類されます。使い方いりこ(煮干し)や鰹節などからとった出汁に味噌を溶いて、野菜や豆腐、ワカメ、しじみなど好みの具材を入れて楽しむ味噌汁は、日本料理の定番として広く普及しています。
また、味噌汁以外にも、サバを味噌や砂糖、みりんなどと一緒に煮込む「サバの味噌煮」や、味噌を溶いた出汁にうどんを入れて煮込む「味噌煮込みうどん」などさまざまな料理の味付けにも使われます。バリエーション-
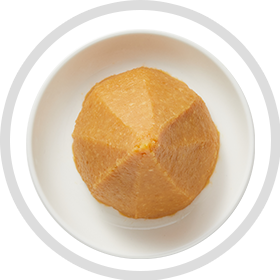
米みそ
-

麦味噌
-

豆味噌
-

調味味噌・(合わせ味噌)
出典:イチビキ公式ウェブサイト
-